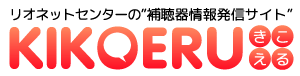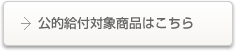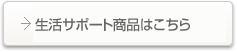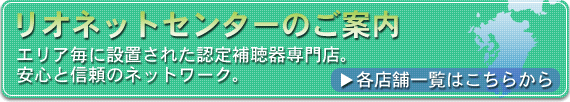公的給付について
店頭にお問い合わせ頂ければ詳しくご説明いたします。
≫各店舗紹介はこちら
補聴器購入費用支給の流れ
・身体の障害の状況により、イヤモールドを必要とする場合は、修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算すること。
・ダンパー入りフックとした場合は、250円増しとすること。
・平面レンズを必要とする場合は、修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を、また、矯正用レンズ、又は遮光矯正用レンズを必要とする場合は、眼鏡の修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算すること。
・重度難聴用耳かけ型で受信機、オーディオシュー、ワイヤレスマイクを必要とする場合は、修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算すること。
・デジタル式補聴器で、補聴器の装用に関し、専門的な知識・技能を有する者による調整が必要な場合は2,000円を加算すること。
すなわち補聴器の購入費が医療費控除の対象となる条件は単に聞こえを補うために使用するという目的ではなく、『医師による治療等の過程で直接必要とされて購入した補聴器の購入』であることが必要です。
詳しくはお近くの税務署へお尋ね下さい。
参考:国税庁ホームページ「医療費控除の対象となる医療費」
お気軽にご相談ください。
≫各店舗紹介はこちら
補助金給付について
障害者総合支援法による補装具費支給制度
障害者総合支援法という法律が、平成25年4月1日から施行されました。この法律は、従来の身体障害者福祉法も包括されたもので、この新しい法律による補装具費(補聴器の購入費用)の支給方法をご紹介します。身体障害福祉法との違い
申請方法等の変更は基本的にありませんが、今まで所得に応じて違っていた自己負担額が、障害者総合支援法では原則一律1割負担となりました。(所得によっては例外もあるようです)補聴器購入費用支給の流れ

| STEP1 | お住まいの市町村の福祉事務所・役場(福祉課)で「身体障害者手帳交付申請書」をもらいます。 その時、窓口で病院の指定を受けます。 |
| STEP2 | 指定の病院で「身体障害診断書・意見書」を書いてもらいます。 ※診断料が掛かる場合があります。 |
| STEP3 | 福祉事務所・役場(福祉課)へ下記書類を提出し身体障害者手帳の申請を行います。 (1) 身体障害者手帳交付申請書 (2) 身体障害診断書・意見書 ※身体障害者手帳交付の適否について判定があります。 |
| STEP4 | 判定の結果、許可が下りれば手帳が交付されます。 |
| 級別 | 現症 |
|---|---|
| 2級 | 両耳の聴力レベルがそれぞれ100デシベル以上のもの(両耳全ろう) |
| 3級 | 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの(耳介に接しなければ大声話を理解し得ないもの) |
| 4級 |
|
| 6級 |
|
聴力レベルと聞こえの度合い
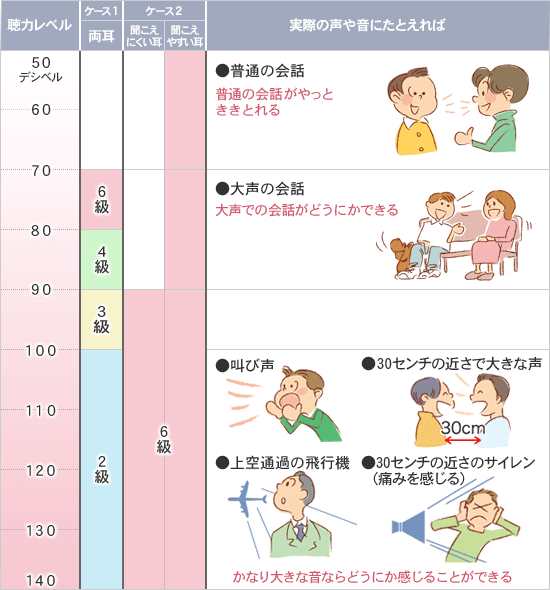

| STEP5 | 身体障害者手帳を持ってお住まいの市町村の福祉事務局・役場(福祉課)へ行き、補聴器給付申請の書類をもらいます。その時、病院の指定を受けます。 |
| STEP6 | 指定の病院で補聴器購入費給付診断書・意見書を書いてもらいます。 ※診断料が掛かる場合があります。 |
| STEP7 | 書類を持ってリオネットセンターへご来店ください。 書類をもとに見積書を発行します。 |
| STEP8 | 「身体障害者手帳」と「印鑑」を持参の上お住まいの市町村の福祉事務所・役場(福祉課)へ下記書類を提出し、補聴器の購入費用の給付申請を行います。 ※補聴器の購入費用給付の適否について判定があります。 (1) 補聴器購入費用給付申請書(市町村の福祉課窓口) (2) 補聴器購入費用給付診断書・意見書(指定病院の判定医) (3) 補聴器の見積書(リオネットセンター) |
| STEP9 | 判定の結果、給付の許可が下りれば「補装具費支給券」がご自宅に届きます。 |
| STEP10 | 「補装具費支給券」と自己負担額の金額、印鑑を持ってリオネットセンターへご来店ください。補聴器をお渡しします。 |
※上記は、基本的な補聴器支給制度の流れであり、各市区町村により異なる場合があります。詳しくはお住まいの市区町村「福祉課窓口」でご確認ください。
※自己負担額は、原則1割負担となります。ただし、所得によっては例外もあります。
| 名称 | 基本構造 | 価格 | 耐用 年数 |
|---|---|---|---|
| 高度難聴用 ポケット型 |
JIS C 5512-2000による。90デシベル最大出力音圧のピーク値の表示値が140デシベル未満のもの。 90デシベル最大出力音圧のピーク値が125デシベル以上に及ぶ場合は出力制限装置を付けること。 |
44,000円 | 5 |
| 高度難聴用 耳かけ型 |
46,400円 | ||
| 重度難聴用 ポケット型 |
90デシベル最大出力音圧のピーク値の表示値が140デシベル以上のもの。 その他は高度難聴用ポケット型及び高度難聴用耳かけ型に準ずる。 | 59,000円 | |
| 重度難聴用 耳かけ型 |
71,200円 | ||
| 耳あな型 (レディメイド) |
高度難聴用ポケット型及び高度難聴用耳かけ型に準ずる。ただし、オーダーメイドの出力制限装置は内蔵型を含むこと。 | 92,000円 | |
| 耳あな型 (オーダーメイド) |
144,900円 | ||
| 骨導式ポケット型 | IEC Pub118-9(1985)による90デシベル最大フォースレベルの表示値が110デシベル以上のもの。 | 74,100円 | |
| 骨導式眼鏡型 | 126,900円 |
備考
・上限価格は電池、骨導レシーバー又はヘッドバンドを含むものであること。ただし、電池については補聴器購入時のみの付属品であり、修理による支給は認められないこと。・身体の障害の状況により、イヤモールドを必要とする場合は、修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算すること。
・ダンパー入りフックとした場合は、250円増しとすること。
・平面レンズを必要とする場合は、修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を、また、矯正用レンズ、又は遮光矯正用レンズを必要とする場合は、眼鏡の修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算すること。
・重度難聴用耳かけ型で受信機、オーディオシュー、ワイヤレスマイクを必要とする場合は、修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算すること。
・デジタル式補聴器で、補聴器の装用に関し、専門的な知識・技能を有する者による調整が必要な場合は2,000円を加算すること。
日常生活用具の給付申請の仕方
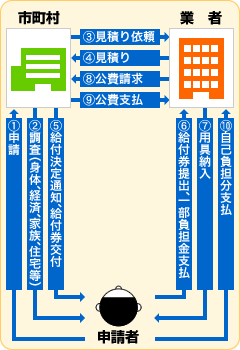 |
各地方自治体(市町村の障害福祉課等)には、申請者の経済状況、身体的状況、家族及び住宅環境等を調査し、必要と認めた場合に「日常生活用具給付券」を交付する制度があります。 給付決定は、障害者本人または障害児の保護者からの申請に基づき市町村が行います。同時に市町村は、障害者総合支援法に基づき申請者の自己負担額を決定します。 日常生活用具の給付手続きは、右記の図のような流れで申請・給付・支払が行われます。 |
補聴器購入の医療費控除について
補聴器購入にかかった費用の医療費控除の条件として、日常生活で最低限の用を足すために供される義手、義足、松葉づえ、義歯を購入するための費用の扱いと同様、医師または歯科医師等の治療または診療等を受けるために直接必要なものであることが要件となります。(所得税基本通達73-3)すなわち補聴器の購入費が医療費控除の対象となる条件は単に聞こえを補うために使用するという目的ではなく、『医師による治療等の過程で直接必要とされて購入した補聴器の購入』であることが必要です。
詳しくはお近くの税務署へお尋ね下さい。
参考:国税庁ホームページ「医療費控除の対象となる医療費」
補聴器の補助金に関するご相談
補聴器の補助金に関するご相談は、お近くのリオネットセンターでも承っております。お気軽にご相談ください。
公的給付について
公的給付についての他のメニュー
公的給付についての他のメニュー